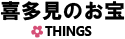 |
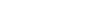 - g01 - g01 |
    
水風呂でお肌ツルツル
「丸正浴場」

世田谷区喜多見4-36-16
tel.3417-6804
『ポンポコ新聞』
第16号より(2004.1)
|
―― もしかしたら地下水を使っていらっしゃるんじゃないですか?
「湯船も上がり湯も地下10mくらいから汲み上げている
地下水100%です。汲み上げたものを一旦タンクに溜めて
薪で沸かします。薪で沸かすとお湯が柔らかくなるんですよ」
―― 水風呂のところに書かれている天然軟水って何ですか?
「5年程前、昔から使っていた井戸が使えなくなったので
深く掘ったら(95m)茶褐色の水が出てきました。
温泉には成分が少し足りなかったものの、天然軟水で、
古代植物のメタケイ酸が含まれていました。湯船に入れる
ほどの量はないので水風呂だけに使っていますが、
試しに自宅で沸かして入ってみたらとても温まるし、
水風呂でもお肌がツルツルになりますよ」
ご主人の橋本久雄さんは氷川神社の神前神楽
(世田谷区の無形文化財)で恵比寿の役をされています。
|
    
ハチミツ専門店
「五十川養蜂園」
いかがわようほうえん

珍しいハチミツがたくさん
狛江市駒井町2-8-2
tel.3480-8383
日月定休
京王ストアの斜向かい
『ポンポコ新聞』
第21号より(2005.5)
|
―― いつ頃お店を始めたんですか?
「父が岐阜で養蜂家をしており、40年前から喜多見に工場を持ち、
問屋さんへ卸していました。店は3年前からです」
―― どんなハチミツがありますか?
「アカシア、レンゲ、ソバ、珍しいものではシナ(日本名は菩提樹)、
ハゼ(実からロウソクの蝋が取れる)など15種類前後です。
しかし岐阜でもレンゲなどが取れにくくなり、ハチミツは貴重です」
―― ハチミツのお勧めは?
「ハチミツにはビタミンC等、身体に良いとされる成分が沢山
入っています。コーヒー、紅茶に入れても癖がないのはアカシア、
レンゲです。梅、ゆず、かりんなどを漬けるにも良いと思います。」
* * *
沢山のハチミツが並び、試食もさせてくれます。
珍しいというシナやハゼを食べてみました。
それぞれの癖がとても美味しく感じられました。
|
    
創業1914年
「岩崎瓦工業」

四代目・岩崎貴夫さん
世田谷区成城1-5-16
tel.3417-1234
『ポンポコ新聞』
第23号より(2005.11)
|
―― 最近、瓦は珍しいですね。
「新築の家で瓦の希望は結構多いんですよ。
耐震性の瓦もありますし、並べ方などの施工法で地震に強く
なっています。屋根全体を覆うような屋根材に比べ、
瓦は1枚壊れたらその1枚を取り替えるというように部分的に
直せるので屋根全体で見れば大変長持ちします」
―― 近所からの注文が多いですか?
「東北や新潟、鹿児島など全国からも注文が来ます。
喜多見周辺では、慶元寺、知行院、宝寿院、そのほか、
江戸東京博物館、黒澤明監督の映画、三谷幸喜作品
『みんなの家』、TVのCMなども多数やっています」
―― 瓦はどこで焼くのですか?
「瓦の産地は埼玉、愛知(三河)で、そこで焼いた瓦を
使っています。この辺りでは昔、宇奈根の海老沢瓦店さん
にも瓦釜があったそうです」
―― 瓦の歴史を教えてください
「瓦は中国から伝わってきたもので、一番古いものは1400年前、
奈良の唐招提寺の屋根に使われ、現在も屋根に乗っています。
江戸時代になり五代将軍綱吉の頃、火事が多かったため、
藁葺き(わらぶき)屋根から瓦葺きにするよう奨励され広まりました。
瓦には色々な種類があります。京都の瓦屋根には錘馗(しょうき)様
が乗っています。沖縄の家の屋根にシーサーが乗っているのと
同じで、魔除け、厄払いのためです。京都にはお寺が多く、
お寺の鬼瓦に対するものです。その昔、中国で楊貴妃が
錘馗様が鬼を踏み潰した夢を見たという話に由来しています。また、
珍しい瓦には、ジェラール瓦というものがあります。
これは、フランス人が横浜に来たときに瓦屋根を見て気に入り、
作らせたものです。喜多見の家にもこの瓦を使っている家があります」
―― 瓦の良い点は何ですか?
「土を焼いてできているので100%天然という事と、湿気の多い日本の
気候風土に合っている事です。家に重さを掛け柱の強度を上げて、
瓦の地厚と風の通る隙間によって断熱しながら通気・換気をしています」
貴夫さんは京都で瓦の勉強をされたそうで
奥深い話を沢山聞くことができました。
夏には今年も区民まつりで鬼瓦作り(型抜)をされるそうです。
http://www.iwasaki-kawara.co.jp/
|
    
次大夫堀公園近く
「小川造園」

にごりや横のケヤキ並木
を剪定する様子
(2005.3撮影)
NHK「おはよう日本」
でも紹介されました。
世田谷区喜多見7-18-13
tel.3415-1128
『ポンポコ新聞』
第33号より(2008.10)
|
――歴史を教えてください。
「父・小川秀吉が始め、私で二代目になります。
父は、農家なのに農業が嫌い、でも植物が好きで、成城にあった
庭善(にわぜん)という大きな植木屋に弟子入りしました。
独立して、成城学園の事務長宅の庭を手入れしたのを初めに、
紹介で仕事が広がっていきました。私達は成城の町とともに歩んで
きたんですよ。成城学園ができた当時、成城の町は1軒300坪が
基本だったのですが、次第に細切れになり、庭の造りも変わって
いきました」
――以前、小川造園さんがにごりやさんのケヤキ並木を
剪定しているのを見かけたことがあります。
「神社やお寺、民家の屋敷林など、保存樹木になるような大きな木
も剪定します。その職人を“空師(そらし)”と言うんですよ」
――喜多見に昔からある木にはどのようなものがありますか?
「ケヤキ、カシ、カキなどがあります。ケヤキの落ち葉は畑の肥料に
なり、枝は薪(まき)になります。特に秋頃から伐る木は水分がなく
締まっていて火力が強いので薪によく、お風呂を焚くのに使われました。
落ち葉も剪定枝も今は廃棄物として燃やされることが多いですが、
昔は肥料として土に還ったんです。カシには防風林の役目があり、
何代も続いている家には必ず植えられていたものです。
カキは禅寺丸という種類で、昔は幹の太いものが結構あったのに、
最近はあまり見なくなってしまいましたねえ。外来の木が多くなりました」
――野川の水を次大夫堀へ引き込む所の掃除も小川造園さんですか?
「ちょっと深くなっているので、大きなコイやナマズ、
スッポンなどが出てきて面白いですよ」
――喜多見の方に伝えたいことはありますか?
「喜多見は歩くのが楽しい町です。こういう環境にせっかく
住んでいるんですから、鉢植え1つでも草花を育てるとか、
生きものを愛する心をもち、潤いのある生活をしてほしいですね」
農閑期に農家の方が植木屋の仕事を手伝うこともあったそうで、
昔は地域の中で、人も自然も上手に循環していたようです。
そんな生活も見直してみたくなりました。
|







